贈与登記
贈与契約書の作成から登記申請まで、
司法書士にお任せください。
無償で(お金の支払いなしで)所有権を譲ることを、贈与といいます。
相続争いの予防や、相続税対策をすることができます。
司法書士が贈与契約書を作成し、登記を申請します。
贈与税について、税理士と同席してのご相談も可能です。
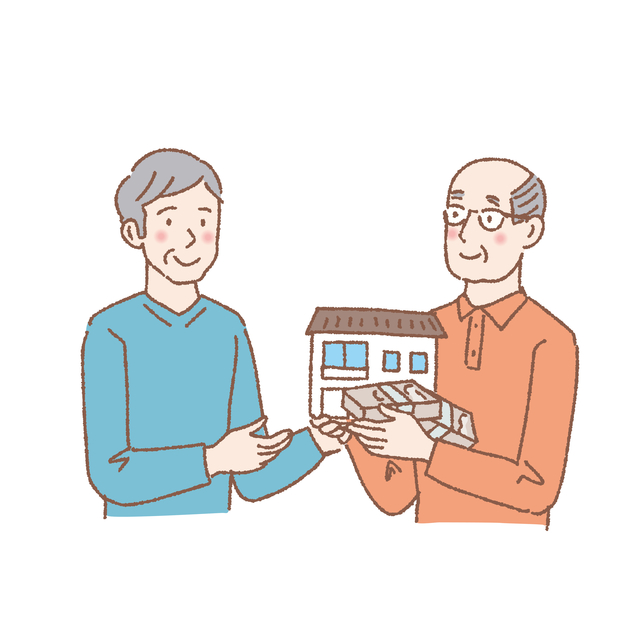
こんなお悩みはありませんか?
贈与契約書を作ってほしい
当事務所では、司法書士が不動産の贈与契約書を必ず作成します。登記完了後に原本をお渡しします。
贈与税を含めた費用が気になる
贈与をすると、贈与税だけでなく、不動産取得税、登録免許税という税金がかかります。一般的な説明はいたしますが、贈与税の申告や相続時精算課税の届出も依頼したい方には、税理士をご紹介します。
名義変更したいが贈与になるのか知りたい
「とにかく名義変更したい」というご要望をいただくことがありますが、代金なしで譲る場合は、基本的に贈与です。
「名義変更=所有権を移転する」ことになりますので、税金に注意が必要です。
このような方もご相談ください
- 親から子へ贈与したい(相続時精算課税)
- 夫婦間で贈与したい(配偶者控除)
- 祖父母から孫へ贈与したい
- 兄弟間で贈与したい
- 数年に分けて贈与したい
贈与税について
暦年課税と相続時精算課税という二つの課税方法があります。
暦年課税
1年間にもらった財産に課税され、年間110万円以下なら贈与税がかかりません。
誰から誰への贈与かによって、2種類の税率があります。
相続時精算課税
選択時に適用されます。相続時精算課税を選ぶと、暦年課税には戻れません。
税金がかからなくても、税務署への申告が必要です。
累計2,500万円までの特別控除と、年間110万円までの基礎控除の二つの控除があり、その金額までは課税されません。(令和6年改正)
(超過分は一律20%で課税されます。)
そして、贈与者が亡くなったときの相続税計算時に、贈与財産の額を相続財産に加えます。
計算した相続税額から納付した贈与税額を引きます。
配偶者控除
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産(または取得資金)を贈与したときは、暦年課税の基礎控除110万に加えて2,000万円までは非課税となります。
税金がかからなくても、税務署への申告が必要です。
よくあるご質問
- 親から贈与を受けますが、親が高齢です。代理で手続きできますか?
-
代理での手続きはできかねますので、必ずご本人とお会いして、意思の確認をさせていただきます。 ご事情によっては出張での対応も可能ですので、ご相談ください。
なお、認知症などによりご本人の判断力が不十分な場合は、贈与の手続きを進めることができません。
微妙な場合は、医師の診断書をご用意いただくこともございます。
- 住宅ローンが残っている不動産を贈与できますか?
-
銀行の承諾が必要なことが多いです。抵当権設定時の契約書をご確認ください。
完済後に贈与するか、事前に承諾を得ることになります。
- 借金があります。差押えを回避するために贈与できますか?
-
犯罪(強制執行妨害目的財産損壊等罪)のおそれがある場合は、受任できません。
贈与が取り消される可能性もあります。(詐害行為取消)
- 権利証をなくしてしまいましたが、贈与できますか?
-
可能です。事前通知という方法を利用します。
必要書類
初回持ち物
以下をお持ちいただければ、詳しい見積もりが可能です。(揃えられる範囲で結構です。)
| 1. 固定資産税の納税通知書 | 毎年5月頃に届くもの |
|---|---|
| 2. 権利証 | 初回はなくても構いません。紛失している場合は、事前通知という方法を使います。 |
| 3. 認印 | (シャチハタ以外) |
| 4. 身分証明書 | 運転免許証、マイナンバーカード、保険証など |
登記の必要書類
事案により多少異なりますので、面談時にご案内します。
事前に把握したい方は、以下をご覧ください。
費用
司法書士の料金
| 報酬(税込) | |
|---|---|
| 基本料金 (贈与契約書を含む) |
52,800円 |
登録免許税
不動産の固定資産評価額の20/1000です。
評価額は固定資産税納税通知書に書かれています。
贈与税
上記「贈与税について」をご覧ください。
不動産取得税
不動産を取得した方にかかる税金です。築年数により軽減があります。
詳しくは各都道府県のホームページをご覧ください。
ご相談の流れ
完了までは、3週間~1か月程度です。
-
01. お問い合わせ
まずは電話、メール、LINEでお問い合わせください。
電話では、「ホームページを見ました」とお伝えいただけるとスムーズです。面談をご希望であれば、日時を調整します。ご不明な点がありましたら、遠慮なくお尋ねください。
-
02. 面談
初回は、当事者の一人(渡す方かもらう方)がお越しいただければ結構です。
見積書を作成しますので、納得されましたらご依頼ください。必要書類をご案内します。また、贈与では税金の検討が必須です。必要に応じて税務署へ相談していただくか、税理士をご紹介します。

-
03. 必要書類の収集
必要書類を集めていただきます。
また、司法書士が贈与契約書等の登記に必要な書類を作ります。 -
04. 署名捺印
贈与契約書と委任状に、署名捺印していただきます。
このとき、司法書士が贈与の意思を確認します。 -
05. 贈与登記の申請→完了
司法書士が法務局へ申請します。
1週間ほどで完了します。完了後の受け取りも司法書士が行います。
依頼者の方が法務局に行く必要はありません。 -
06. ご返却・完了
登記簿で、登記結果を確認します。
登記識別情報通知(昔の権利証にあたるもの)をお渡しして完了です。配偶者控除や相続時精算課税を使うときは、贈与税の申告をお願いします。
専門家に任せたいという方には、税理士をご紹介します。
